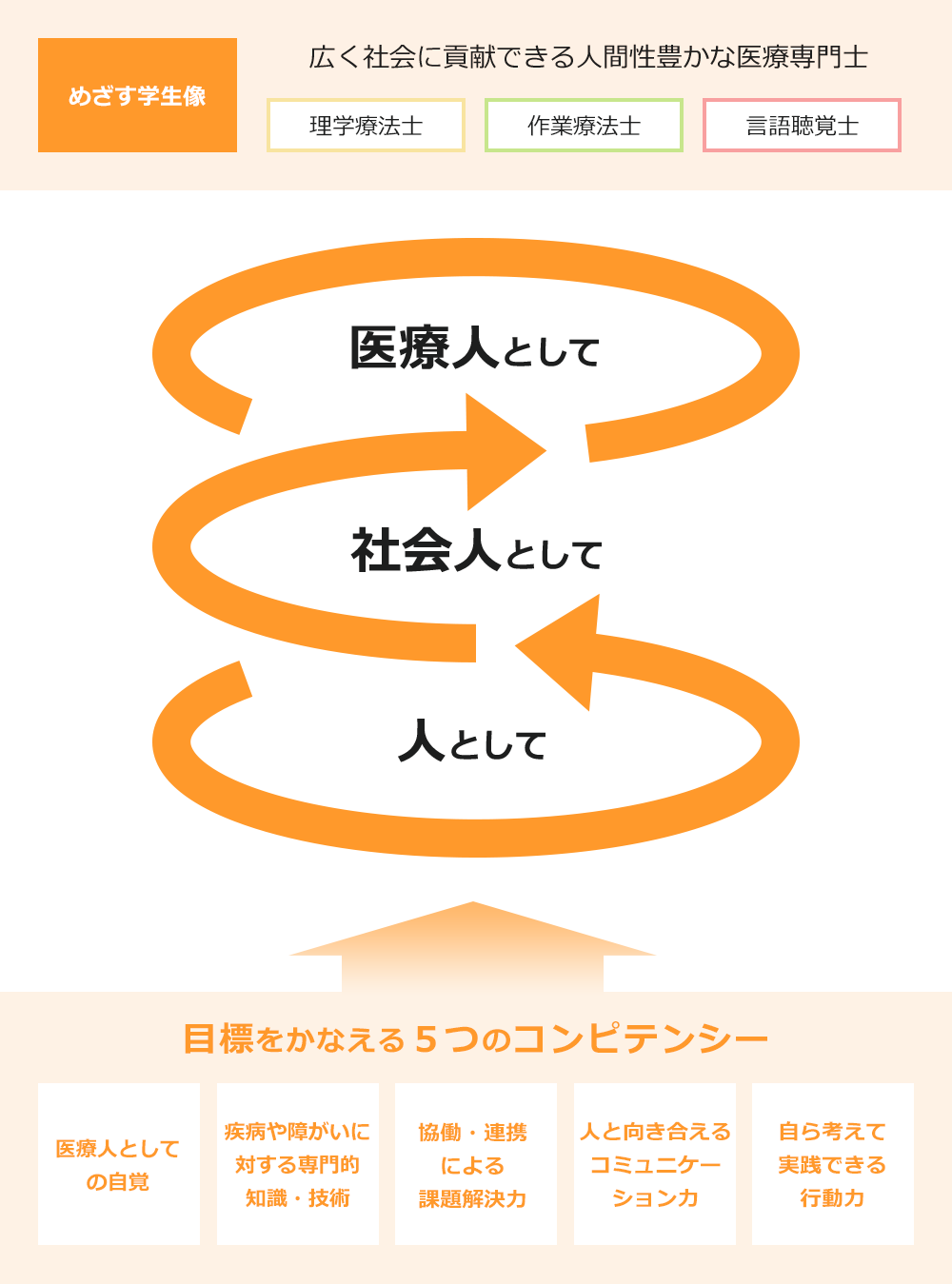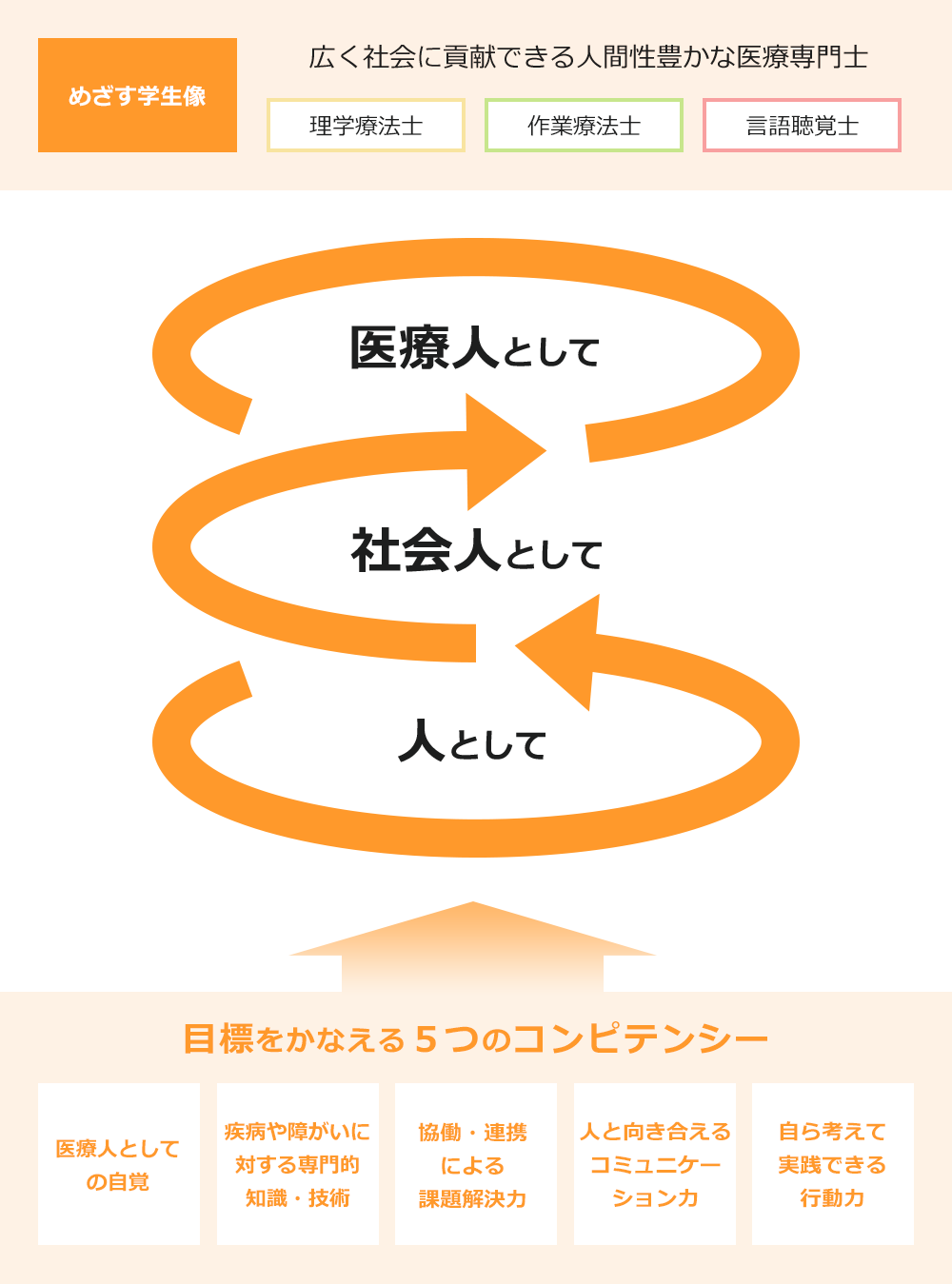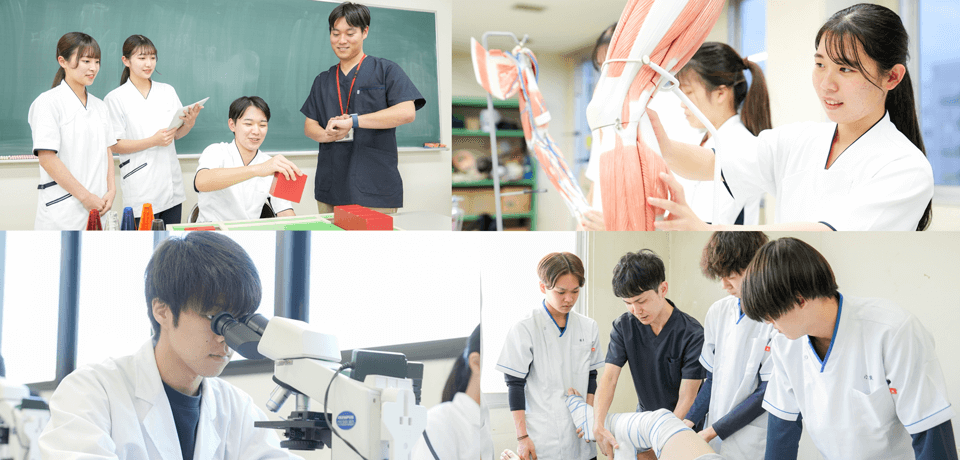概要
本校の作業療法士科は、大分県初の作業療法士養成課程として平成7年4月に開校しました。
卒業生は大分県をはじめ全国の医療・福祉・介護・保健分野で活躍しています。
その領域は広く、身体障害から発達障害、老年期障害、精神障害まで多岐にわたっています。
本科は専門職として、実践力を高めるため臨床経験を大切にした授業形態をとり、世界作業療法士連盟の認定も受けています。
また、リハビリテーションにおけるチーム連携が必須な現在、理学療法士科、言語聴覚士科併設を利点に3科合同の専門職連携教育(Inter Professional Education:IPE)を導入し、社会のニーズに対応する教育を行っています。1クラス30名と小規模ながらもその利点を活かし、全教員が学生一人一人と向き合いきめ細かな指導で、顔の見える教育を展開しています。
挨拶
本校は「誰かのために・・・・・」と思う皆さん方を応援します。
大分リハビリテーション専門学校には、理学療法士科、作業療法士科、言語聴覚士科の3学科が設置されています。(全科3年制)開校当初から、「広く社会に貢献できる、人間性豊かな医療専門士の養成」を教育目標に掲げ、本学園の教育の精神である「誠実・丁寧・知力」のもと、知識や技術の習得だけにとどまらず、人としての成長を促し、誰からも愛される医療人の育成を目指してきました。
そのため本校では少人数制で、きめ細かな指導を行うと共に個別指導にも力を入れています。共生社会の推進に向けて、多領域の講師が授業を担当し、それぞれが現場経験を活かした授業を進めています。また、チーム医療に対応するため、3学科の特性を生かし、各々が高い専門性を持ちながら、目的と情報を共有し理解と連携を深め、互に学びあうIPE 教育(多職種連携教育)も積極的におこなっています。
このように現場を想定した取り組みは、国家試験においても効果が表れ、毎年全国の合格率平均を大きく上回り、高い合格率を誇っています。また、求人も多く就職率は100%です。リハビリテーション専門士は、今や地域・社会において必要不可欠な存在となっています。
校長 藤岡 晋三
リハビリテーションとはその人らしさを取り戻すプロフェッショナルです
こころとからだ、そしてコミュニケーションが回復し、自分らしさを取り戻せたら・・・
そんな素敵なことはありませんよね。「リハビリテーション」とは再びその人らしさを取り戻すお仕事です。
“難しそう”“自分ができるかな~?” そんな不安を抱く方もいます。
ここは(本校)、貴方のチャレンジに伴走しながらリハビリテーションの専門職(セラピスト)になれるようにお手伝いします。
「やれるだろうか?」から「やれる気がする!」そんな貴方の成長と「セラピストになる」という目標を一緒に達成しましょう。
教育部長 日隈 武治

- 学科長
- 後藤 英子
- 担当科目
-
- 作業療法概論
- 基礎作業学Ⅲ(分析)
- 発達評価学 など
作業療法士は、「ひとのくらし」を科学する「こころとからだ」の専門家。対象者にとって「意味ある作業」を介して人々の健康と幸福を促進するために、学校では解剖学、生理学、精神医学などの医学の講義は勿論、生活環境論や地域リハビリテーション論などの興味深い学問を学びます。また、多くの演習・実習を通して、多様な価値観に触れ、豊かな心をもった作業療法士を育成します。対象者を支援できる作業療法士を目指して一緒に頑張りましょう。

- 教務主任
- 矢野 高正
- 担当科目
-
作業療法士は、「こころとからだ」の両側面から対象者の生活を支える専門家です。何事も客観的に見極める冷静さと、対象者に寄り添う情熱を兼ね備えた作業療法士を、私たちと一緒に目指しましょう。
- 課程名医療専門課程
- 学科名作業療法士科
- 修業年数3年
- 区分昼間
- 入学定員30名(男女)
- 単位数120単位
- 時間数3210時間
在学中に取得できる資格
- 初級障がい者スポーツ指導員(日本障がい者スポーツ協会)
卒業時に得られる資格・称号
- 作業療法士国家試験受験資格
- 専門士(医療専門課程)
教育目標
大分リハビリテーション専門学校は、リハビリテーションを担う専門職の総合的養成施設として、「広く社会に貢献できる人間性豊かな医療専門職を育成する」ことを教育目標としています。この目標を実現させるため、下記の点に重点をおいて人材の育成をめざしています。
1.医療人としての自覚
医療人として、人の尊厳や人権を尊重し、倫理観や使命感を持った人材を育成する。
2.疾病や障害に対する専門的知識,技術
科学的根拠に基づいた専門的知識・技術を習得し、臨床に応用できる人材を育成する。
3.協働,連携による課題解決能力
自らの役割及び他職種の役割を理解し、チームの一員として協働し課題解決できる人材を育成する。
4.人と向き合えるコミュニケーション力
自身の考えを適切に表現でき、他者の言葉に耳を傾け、誠実に人と向き合えるコミュニケーション力を持った人材を育成する。
5.自ら考え実践できる行動力
自らの行動に責任を持ち、主体的に考え実践できる人材を育成する。